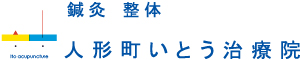耳鳴り(Tinnitus)の西洋医学的原因
耳鳴りは、自覚的耳鳴(本人のみ聞こえる)と他覚的耳鳴(外部からも検出可能)に分けられ、多くは自覚的耳鳴です。
(1)主な病態
-
内耳障害
-
蝸牛(かぎゅう)の有毛細胞の損傷(騒音曝露、加齢性難聴=老人性難聴)。
-
突発性難聴やメニエール病による内リンパ水腫。
-
-
聴神経・中枢神経系の異常
-
聴神経腫瘍(前庭神経鞘腫)や脳幹障害。
-
-
血管性要因
-
耳周辺の血流障害(動脈硬化、高血圧、貧血)。
-
-
筋骨格系の影響
-
顎関節症(TMD)や頸椎異常による関連痛・神経圧迫。
-
(2)耳鳴りの種類
-
高音性耳鳴(キーン、ピー):加齢性難聴、騒音性難聴に多い。
-
低音性耳鳴(ブーン、ゴー):メニエール病、中耳炎関連。
めまい(Dizziness/Vertigo)の西洋医学的原因
めまいは、回転性(Vertigo)と非回転性(Dizziness)に分類され、原因は多岐にわたります。
(1)末梢性めまい(内耳・前庭神経由来)
-
良性発作性頭位めまい症(BPPV)
-
耳石(炭酸カルシウム結晶)が半規管に入り込むことで発症。
-
-
メニエール病
-
内リンパ水腫により、回転性めまい+耳鳴り+難聴の3徴候。
-
-
前庭神経炎
-
ウイルス感染などで前庭神経が炎症を起こし、強いめまいが持続。
-
(2)中枢性めまい(脳幹・小脳障害)
-
脳梗塞/脳出血(特に椎骨脳底動脈循環不全)。
-
多発性硬化症、小脳腫瘍など。
(3)その他の原因
-
起立性低血圧(自律神経失調症)。
-
薬物性めまい(抗てんかん薬、降圧薬など)。
-
心因性めまい(パニック障害、不安症)西洋医学的治療の限界と鍼灸の役割
西洋医学では、原因に応じて以下の治療が行われますが、根本的解決が難しいケースも少なくありません。
-
薬物療法
-
メニエール病→利尿薬、抗めまい薬(ベタヒスチンなど)。
-
BPPV→耳石置換法(エプリー法)。
-
突発性難聴→ステロイド、血流改善薬。
-
-
手術療法
-
聴神経腫瘍、難治性メニエール病(内リンパ嚢解放術など)。
-
鍼灸が有用なケース
-
原因不明の慢性耳鳴り
-
ストレス・自律神経失調によるめまい
-
薬物療法で改善しないメニエール病の補助療法
-
頸部コリや血流不全が関与する症例
東洋医学的な原因
耳鳴りやめまいは、主に以下のような「臓腑」や「経絡」の不調と関連すると考えられます。
-
腎虚(じんきょ):東洋医学で「腎」は耳と深く関わり、加齢や過労で腎精が不足すると耳鳴りやめまいが起こりやすい。
-
肝陽上亢(かんようじょうこう):ストレスなどで肝の気が上昇し、頭部に熱がこもると耳鳴りやめまいが生じる。
-
痰湿(たんしつ):水分代謝の異常により痰湿が内耳に影響を与える(メニエール病など)。
-
気血不足:貧血や虚弱体質で脳や耳への栄養が不足すると症状が出やすい。
鍼灸治療のポイント
※首や肩の筋緊張緩和、耳周りの局所血流の改善、全身調整のツボを組み合わせて治療プランを組み立てます。
-
耳周囲のツボ
-
聴宮(ちょうきゅう)、聴会(ちょうえ)、耳門(じもん):耳の周囲にあり、直接的に耳の機能を調整。
-
-
全身調整のツボ
-
百会(ひゃくえ):頭頂部のツボでめまいや頭部の気の流れを改善。
-
風池(ふうち):首の付け根のツボで、めまいや頭痛に効果的。
-
太谿(たいけい):内くるぶし近くで「腎」を補う。
-
足三里(あしさんり):消化機能を強化し気血を補う。
-
三陰交(さんいんこう):肝・腎・脾のバランスを整える。
-
-
治療期間:慢性の耳鳴りやめまいには、継続的な治療(週1~2回、数ヶ月)が必要な場合があります。
-
生活習慣の改善:ストレス軽減、睡眠不足の解消、塩分・カフェインを控えるなど。
エビデンス(研究結果)
-
メニエール病や突発性難聴に対する鍼灸の有効性を示す臨床研究があります。
重症例の場合は、西洋医学的な治療と併用することが効果的なことが多いです。 -
ストレス性の耳鳴りには、鍼灸が自律神経を安定させる効果が期待できます。