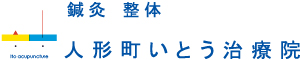春は「気」と「風」が動く季節 〜東洋医学に学ぶ春の養生〜
こんにちは。
人形町いとう治療院の伊藤です。
3月までは目まぐるしい寒暖差に振り回された感じでしたが、今月になって夜の帰り際などでも寒さを感じなくなりました。
一方で春になると、気温や日照時間の変化に伴って、私たちの心身にもさまざまな影響が現れます。
「なんとなく疲れやすい」「気分がすぐれない」「頭が重い、ふらつく」といった不調を感じる方も少なくありません。
東洋医学では、こうした春特有の体調変化に対して、自然との関係を重視しながら、独自の視点で原因と対処法を考えてきました。
今回は東洋医学の観点から、春を健やかに過ごすための養生法をご紹介します。
春は「陽の気」と「風」の影響を強く受ける季節
東洋医学では、自然界の動きと人間の身体は密接につながっていると考えます。
春は、冬の寒さで閉じこもっていた「陽の気」が上昇し、外に向かって広がっていく季節。
このように気が動き出すことを「発陳(はっちん)」と呼び、万物が芽吹くように、私たちの体内でもエネルギーが活発に動き始めます。
同時に、春は五行でいうところの「木」に属し、自然界では「風」が司る季節でもあります。
風は動きを持ち、変化しやすく、上へと昇る性質を持つため、体内の陽気もそれに伴って上へと向かいやすくなります。
「肝」と「風」の関係 〜頭部の症状に注意〜
春は五臓の中では「肝」と深い関わりがあり、肝は気の巡りを調整する「疏泄(そせつ)」の働きを担っています。
この季節は、肝の活動が盛んになる一方で、「風」の影響により体内の陽気が頭部へと昇りやすくなります。
このような状態になると、特に以下のような“上部”の不調が起こりやすくなります:
-
頭痛・めまい・ふらつき
-
顔や目のほてり、目の疲れ
-
耳鳴りや肩・首の緊張
-
不眠や夢が多い
これらは「肝風内動(かんぷうないどう)」と呼ばれる状態の一種で、気や血の流れが乱れることで、風のような症状(揺れる、動く、急に現れる)が現れるのが特徴です。
春を健やかに過ごすための養生法
こうした春の体調変化に対応するには、日々の生活の中で気の流れを整え、過度に陽気が上昇しないよう工夫することが大切です。
・朝の時間を有効に使い、適度に身体を動かす
軽い運動や深呼吸は、気の巡りを促し、冬場に溜め込んだ体内の気を外に発散させる作用があります。
また「上に昇りすぎた気」を全身に分散させるのにも役立ちます。
・春の旬の食材を取り入れる
緑色の野菜(肝の色)や、酸味のある食材(肝の働きを引き締める)を意識的に摂りましょう。
菜の花、せり、春キャベツ、レモン、酢の物などが養生に適しています。
・首から上を冷やさない/風を直接受けない
春の風は一見心地よいものですが、東洋医学では「風邪(ふうじゃ)」の入り口とされ、頭痛やめまいの原因となることがあります。
特に首の後ろや頭部が冷えないよう気を配りましょう。
・感情の波に振り回されない
肝は「怒」と関係し、感情に左右されやすい季節です。
意識的にリラックスする時間を作り、音楽や散歩、瞑想などで心を落ち着けるようにしましょう。
鍼灸による春のケア
鍼灸では、「気血の巡り」や「肝の調整」、そして「風による症状」の緩和を目的とした施術を行います。
春に現れやすい頭痛やめまい、不眠、肩こり、精神的不安定などに対し、身体の内側から整えていくのが特徴です。
特に「なんとなく不調が続いている」「病院に行くほどではないが調子が悪い」という方には、鍼灸の養生的なアプローチが適しています。
おわりに
春は本来、心身が自然と活動的になり、成長や変化に向かって動き出す季節です。
しかし、「陽気の上昇」や「風の影響」が強くなるこの時期は、体内のバランスが乱れやすくもあります。
不調を感じたときは、無理をせず、まずはご自身の状態を見つめ直す時間を持つことが大切です。
自然の流れに寄り添いながら、心と体を整える春の過ごし方を、ぜひ意識してみてください。
======================================
【東京都中央区 日本橋人形町・水天宮前の鍼灸・整体治療院】
鍼灸 整体 人形町いとう治療院 Ito Acupuncture
肩こり・腰痛・自律神経失調症・ランニング障害でお悩みの方が大勢いらしています
東京都中央区日本橋人形町1-10-5 富士ビル2階
TEL 03-6883-3598
予約・問い合わせフォームより24時間受付中